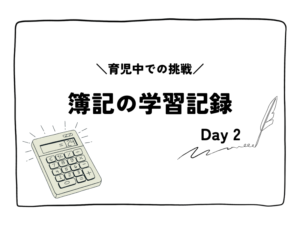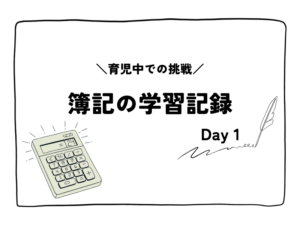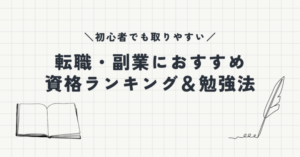「思ったより難しかった」「勉強の方向性がわからない」と感じている方へ
令和6年度以降の保育士試験では、出題傾向が少しずつ変わってきています。
これまでのようにテキストを丸暗記するだけでは対応しづらくなり、「理解して答える」問題が増えているのが特徴です。
今回は、これから試験を目指す方に向けて、最近の傾向と勉強のポイントをわかりやすくまとめました。
■ 保育士試験の基本ルールをおさらい
- 筆記試験は9科目。すべて6割以上の得点で合格。
- 特に「教育原理」と「社会的養護」はセット科目のため、両方6割以上でないと不合格になります。
- 実技試験は3分野のうち2分野を選択して受験します(音楽・言語・造形)。
■ 出題傾向①:「保育所保育指針」からの出題が増加
令和6年度後期試験では、保育原理の問題のうち14問が保育所保育指針からの出題でした。
特に「第1章 総則」「第2章 保育の内容」は毎回問われやすい部分です。
✅ ポイント
保育所保育指針の言葉をそのまま覚えるよりも、「なぜそう書かれているのか」「どんな場面を想定しているのか」を理解しておくと応用問題にも対応しやすくなります。
■ 出題傾向②:法改正・統計データ系の問題が増えている
- 「児童福祉法」や「配置基準」の改正
- 「保育所等関連状況取りまとめ(令和5年4月1日版)」などの最新データ
こうしたリアルタイムな内容が出題される傾向にあります。
✅ ポイント
試験直前に各省庁サイトや信頼できる資格サイトで、最新の法改正・数値をチェックしておくのが◎。
テキストの改訂が追いつかない年もあるため、最新年度の内容を押さえる意識を。
■ 出題傾向③:「発達・虐待・心の問題」に関する出題が増加
令和6年後期の「保育の心理学」では、
- 自閉スペクトラム症
- DV(ドメスティック・バイオレンス)
など、実際の現場に近いテーマが多く出題されました。
また、グラフや資料を読み取る考察型問題も登場しています。
✅ ポイント
「知っている」よりも「どう考えるか」を問われる設問が増えているため、ケーススタディ問題にも慣れておきましょう。
■ 出題傾向④:実技試験は“定番テーマ+表現力重視”
実技では大きな出題変更はなく、
- 【造形】保育の一場面を描く
- 【言語】3歳児向けの物語を話す
といった定番形式が継続中。
ただし、「絵の構成」や「話し方の一貫性」など、表現力の完成度が重視される傾向があります。
■ 今後の試験対策で大切な3つのポイント
- 指針の「意味理解」を重視する
丸暗記ではなく、「なぜそうなのか」を言葉で説明できるレベルに。 - 最新の法改正・データを必ずチェックする
公式サイト・ニュースリリースを定期的に確認。 - “考える力”を育てる問題演習を取り入れる
資料読解や事例問題で応用力を磨く。
まとめ
保育士試験は年々、現場での実践力や社会の変化に合わせた出題が増えています。
「知っている」だけではなく、「理解して答える」姿勢が求められる試験です。
焦らず、少しずつ“根拠を持って説明できる勉強法”に切り替えていきましょう。