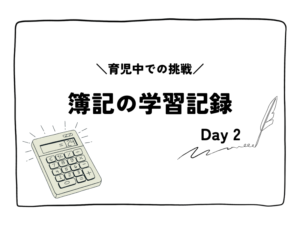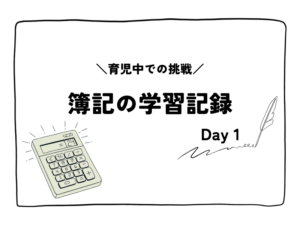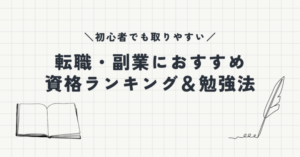「心理学だけ点数が取れない…」という人へ
保育士試験の中でも「保育の心理学」は苦手意識を持つ人が多い科目です。
専門用語が多く、似た名前の心理学者もたくさん出てきますよね。
でも実は、「用語の意味」と「子どもの姿」をつなげて考えられるようになると、グッと理解しやすくなるんです。
この記事では、出題傾向・苦手克服ポイント・おすすめの覚え方をまとめました。
■ 出題傾向をおさらい
「保育の心理学」は、主に次の4つのテーマから構成されています。
- 発達の段階と特徴(乳幼児期・思春期など)
- 発達理論(ピアジェ・エリクソン・ヴィゴツキーなど)
- 観察・評価・アセスメント
- 保育実践との結びつき(保育所保育指針との関連)
令和6年度後期試験では、「自閉スペクトラム症」「愛着形成」「DVと子どもの心」など、発達や心の問題に関する応用問題が目立ちました。
つまり、「理論だけでなく現場での理解」が問われています。
■ 苦手克服ポイント①:心理学者を「人物」で覚える
多くの人がつまずくのが「誰がどんな理論を言っていたか」問題。
ポイントは、“人の顔を思い浮かべながら覚える”こと。
| 心理学者 | 理論・キーワード | イメージ |
|---|---|---|
| ピアジェ | 認知発達理論(感覚運動期→形式的操作期) | 「子どもは小さな科学者」 |
| エリクソン | ライフサイクル8段階 | 「信頼vs不信」などの対立構造 |
| ボウルビィ | 愛着理論 | 「ママとの絆が心の土台」 |
| ヴィゴツキー | 最近接発達領域・支援(足場かけ) | 「おとなが支えると伸びる」 |
✅ 覚え方のコツ:
名前だけでなく、「どんな考え方だったか」を子どもの行動で想像する。
例:「2歳児がママの真似をする」→ ピアジェの模倣学習かな?と結びつける。
■ 苦手克服ポイント②:図・表で整理する
文章だけで覚えようとすると混乱します。
発達段階(年齢ごとの特徴)や理論の比較は、ノートに自分の言葉で表にして整理するのが一番効率的。
例:ピアジェとエリクソンの違いをまとめる表
→ 「年齢」「キーワード」「課題」を並べるだけで、問題文が理解しやすくなります。
| 理論家 | 年齢 | キーワード | 主な課題・特徴 |
|---|---|---|---|
| ピアジェ | 乳児〜成人 | 認知発達理論 | 感覚運動期、前操作期、具体的操作期、形式的操作期を通して、思考や認知能力が発達する。論理的思考や抽象的思考の発達段階を問う。 |
| エリクソン | 乳児〜老年期 | 心理社会的発達8段階 | 信頼vs不信、自律性vs恥・疑惑、主体性vs罪悪感、勤勉性vs劣等感、同一性vs役割拡散、親密性vs孤立、生成性vs停滞、統合性vs絶望。各段階での心の課題と社会的関わりを問う。 |
■ 苦手克服ポイント③:「現場とのつながり」を意識する
最近の試験では、「心理学の理論をどう保育に活かすか」という出題が増えています。
たとえば、
Q:「子どもの自立を支える保育士の関わりとして最も適切なのはどれか」
このような問題は、「発達理論の知識+実践イメージ」で解けます。
✅ ポイント
理論を“暗記”ではなく、“保育の現場でどう使うか”をイメージする。
実際の子どもの行動(友達とケンカ・ママに甘える・挑戦する)を想像すると答えやすくなります。
例:ピアジェの認知発達理論
| 子どもの行動 | 発達段階 | どう考えるか(理論の活用) |
|---|---|---|
| 2歳がブロックを積み上げて崩す | 前操作期 | 「ものの恒常性」や「原因と結果の理解」がまだ完全ではない段階。遊びを通して論理的理解が発達していく。 |
| 5歳がごっこ遊びで“おままごと”をする | 前操作期 | 「象徴機能」を使って、想像力を発揮している。先生は言葉で説明するより見守りや補助で発達を促せる。 |
| 7歳が数や順序を考えてゲームする | 具体的操作期 | 論理的思考が使える段階。ルールを守って遊べるかを観察することで、認知発達の理解につなげられる。 |
例:エリクソンの心理社会的発達
| 子どもの行動 | 発達段階 | どう考えるか(理論の活用) |
|---|---|---|
| 1歳がママに甘える・泣く | 信頼vs不信 | 保育者の適切な応答で「信頼感」を育むことができる。安心できる環境作りが課題。 |
| 3歳が友達とおもちゃの取り合いでケンカ | 自律性vs恥・疑惑 / 主体性vs罪悪感 | ルールを伝えつつ、自己主張の方法をサポート。自分の行動に責任を持てるよう導く。 |
| 5歳が新しい遊具に挑戦する | 主体性vs罪悪感 | 「やってみよう」と挑戦する気持ちを認め、失敗しても支援することで自信を育む。 |
■ 苦手克服ポイント④:過去問を「解く→解説を読む→もう一度解く」
心理学は、インプットよりアウトプット型の勉強法が効果的です。
- まずは時間を計って過去問を解く
- 解説を読んで「なぜそうなるか」を理解
- 1週間後にもう一度同じ問題を解く
このサイクルを繰り返すだけで、“似た問題が出たときに自然と答えられる”ようになります。
■ まとめ|「理解できる」と心理学は一気に得点源になる
心理学は最初こそ難しく感じますが、理解すれば最も安定して点が取れる科目です。
用語を丸暗記するよりも、「子どもの姿とつなげて覚える」ことで一気に楽になります。
焦らず、少しずつ「人の理論」と「子どもの発達」を結びつけながら進めてみてくださいね。