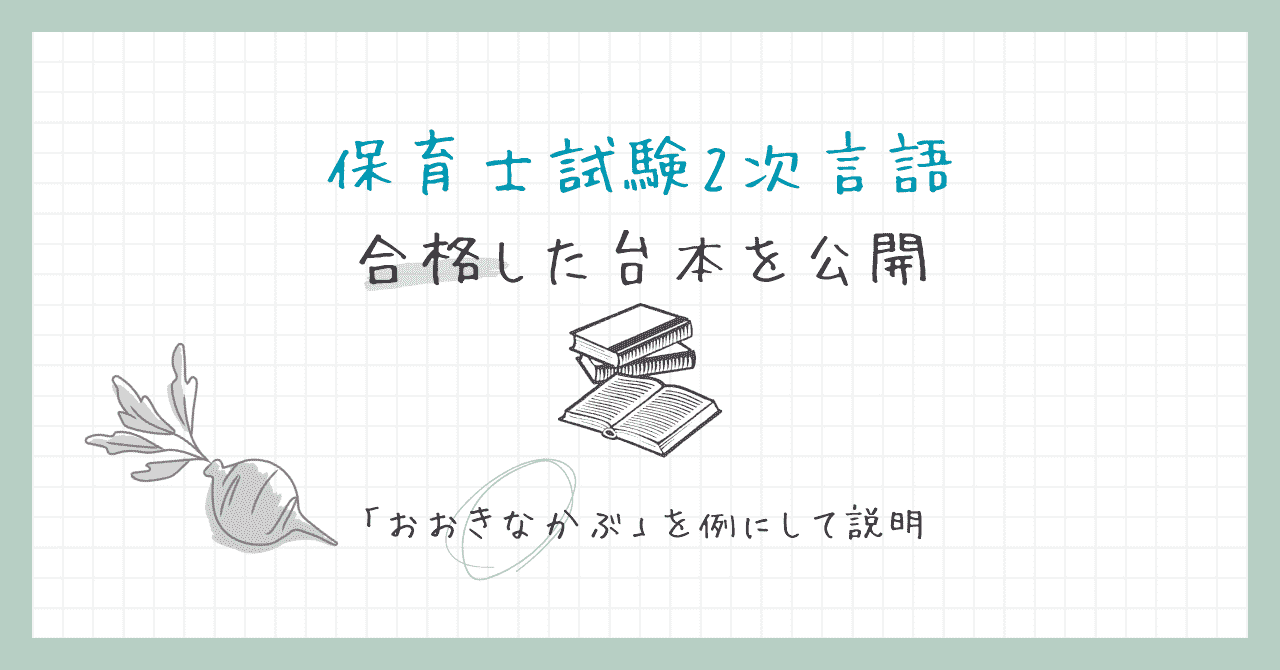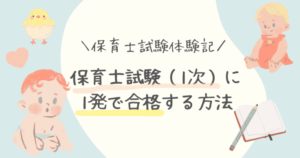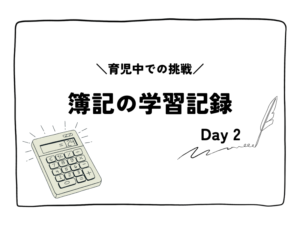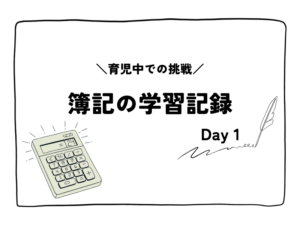こんにちは!ここぽてとです。
保育士試験の実技試験(言語)に合格しました!
本記事では、私が実践した練習方法や当日のポイントを詳しく解説します。
「どう練習すればいいの?」
「本番の流れってどんな感じ?」
そんな疑問を持つ方に向けて、役立つ情報をまとめました。
ぜひ最後までチェックしてください!

ちなみに、実技試験の言語は50点中の36点で合格でした!
実技試験「造形」に関する記事はこちら↓
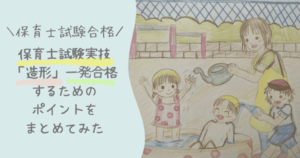
【保育士試験・2次】言語合格のポイント
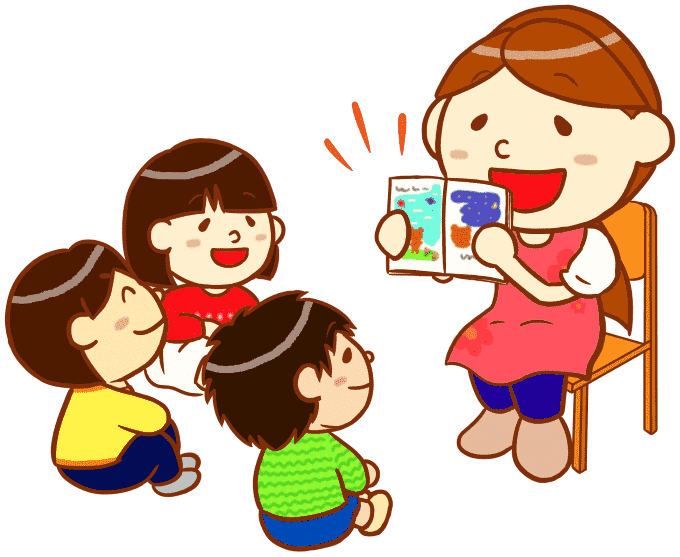
子どもは15人程度が自分の前にいることを想定
目線は椅子に見立てたを交互に見る感じで試験官を見ないようにします。
あくまで目の前の子どもに話しをする感じで話すと、視線の中に試験官が入ってこなくなるので、緊張も解けて話しやすくなります。
3歳の子どもがおはなしの世界を楽しめるように3分にまとめる
おおきなかぶは本当は「孫がおばあさんをひっぱって、おばあさんがおじいさんをひっぱって」など、人物がひっぱるシーンがたくさんあります。
緊張すると間違えそうだったので、「おじいさんとおばあさんと孫が力を合わせて」など表現を変えています。
要はあらすじを崩さなければOK。
3歳の子ども対象だったので、犬や猫の動物を「いぬくん」「ねこちゃん」と擬人化しました。
適切な身振り・手振りを加える
「おおきなかぶ」はセリフが少なく淡々と話すと盛り上がりにかけるので、「大きくて太ったかぶ」のところは、ジェスチャーでおおきなかぶを再現しました。
他にも、かぶをひっぱるときは苦しそうに引っ張っるジャスチャーをし、抜けたときの「やったー!」はとても嬉しそうに話しました。
表情が見えないということもあるので、動きをつけながら、少しオーバー気味に話すのがポイントです。
笑顔を作る(目を細めて話す)
私が受験したときは、マスクを着用して話すのが義務でした。
練習時にお話ししている様子を動画にとったのですが、笑顔で話しているはずなのに、全然笑顔がわからない!
マスクをして話すと笑顔で話したところで相手に伝わらないということを実感しました。
その上、本番は緊張するので、笑顔作るのも大変です。
なので、私は目を細めて、声は元気で弾んでいるような形で話しました。
目を細めて話すことで笑顔で話している風に見えますのでおすすめです。
お話はどれがいい?
個人的には自分がよく知っていて、話しやすいと思ったお話が良いかと思います。
声の使い分けが苦手で、セリフが少ないものがよければ、「おおきなかぶ」がおすすめです。
ただ、「おおきなかぶ」はナレーションが多く、単調になりやすいので、その分動きや読み方に強弱をつけましょう。
実際に使用した台本(大きなかぶ)
実際合格できた台本です。
1週間前に覚え始め、家では大きな声を出せないので、カラオケボックスで何も見ずに動きをつけて練習しました。
その時に、(かなり恥ずかしいですが)友達に撮影してもらって、改善が必要な所(表情や声の大きさ、強弱など)を見つけて改善。
結果、本番で50点中36点での合格でした!
特に力強く話したところは太字にしています。
今から「おおきなかぶ」のお話をするね。
むかーしむかしのお話です。
おじいさんがかぶのたねをまきました。
「おおきなおおきなかぶになあれ、あまいあまいかぶになあれ。」
すると、おじいさんよりも大きくて太った大きなかぶができました。
「ようし、ぬいてみよう。」
おじいさんは、かぶをひっぱります。
「うんとこしょ、どっこいしょ。」
かぶは抜けません。
「私も手伝いますよ。」
おばあさんが来てくれました。
おじいさんとおばあさん、二人で力を合わせてかぶをひっぱります。
「うんとこしょ、どっこいしょ。」
しかし、かぶは抜けません。
「私も手伝うわ。」
孫も来てくれました。
おじいさんとおばあさんと、孫が三人で力を合わせてかぶをひっぱります。
「うんとこしょ、どっこいしょ。」
ところが、かぶはぬけません。
「ぼくも手伝うわん!」
力もちのいぬくんも来てくれました。
おじいさんとおばあさんと孫といぬくん、四人で力を合わせてひっぱります。
「うんとこしょ、どっこいしょ。」
それでもかぶはぬけません。
「わたしも手伝うにゃー。」
ねこちゃんも来てくれました。
おじいさんとおばあさんと孫といぬくんとねこちゃん、五人で力を合わせてひっぱります。
「うんとこしょ、どっこいしょ。」
それでも、かぶはびくともしません。
「どうしよう。困ったなあ。」
「ぼくも手伝うちゅー。」
ねずみくんも来てくれました。
おじいさんとおばあさんと孫といぬくんとねこちゃん、六人で力を合わせてひっぱります。
さあ、今度は抜けるでしょうか?
「うんとこしょ、どっこいしょ。うんとこしょ、どっこいしょ。うんとこしょ、どっこいしょ。」
すると、そのときです。
「すぽーん!」
とうとう、大きなかぶは抜けました。
「やったー!!」みんな大喜びです。
その夜、みんなでかぶのスープをお腹いっぱい食べましたとさ。
めでたしめでたし。
最初に何のお話を始めるか言わないと減点になる可能性があるので、気を付けましょう!
本番当日気を付けること
服装
服
清潔感のあるきれいめなカジュアルスタイルが無難です。
待ち時間が長いので、温度調節のために、羽織れるものがあると良いかと思います。
私は、ユニクロの青と白の縦じまの襟があるシャツブラウス(昔のローソンのユニフォームみたいなシャツです)ベージュのチノパンをはいていきました。
スーツを着ている方は殆どいませんでした。
ジーンズのようにカジュアルすぎても良くないようで、ジーンズで受験に来てる方もあまりおられませんでした。
靴
夏受験の時はパンプスやスニーカーの型が多かったです。
ちなみに私は黒のスニーカーを履いていきました。(プーマのスニーカー)
カバン
いつもの通勤で使うMOZのリュックで向かいました。色はベージュです。
普通の肩掛けカバンを持っている方がかなり多い印象ですが、リュックの方もいました。
「造形」受験の方は、色鉛筆など持ち物があるので、ある程度物がたくさん入るカバンの方が良いかもしれません。
あと、後述しますが、水筒をたくさん持っていった方が良いので、大きめカバンがおすすめ。
時間をつぶせるものを持っていく
当日にならないとわからないのですが、「造形」+「言語」を受験する人は、「造形」+「音楽」で受ける人よりも待ち時間が長いです。
私は、5時間待ちくらいでした(笑)
練習もできないし、緊張疲れにも繋がるので、リラックスできるよう時間を潰せるものを持っていっておいた方が良いです。
飲み物は多めに持っていく
先ほども申した通り、待ち時間がとても長い可能性があります。
本番で緊張するので喉が渇くのでお水を多めに持って行っておいた方が安心です。
(私は途中足りなくて買いに行きました)
本番の流れ
言語は1時間前に待機室で待つことができます。
待機していたら、20分前に案内係の人に試験室の前に誘導されます。
試験室の前には椅子があり、5人ずつ座って待ちます。
前の人のお話の声が聞こえてくるので余計に緊張するかもしれませんが、リラックスを心がけましょう。
- 自分の番が回ってきたら、ドアを3回ノックします。
- 「どうぞ。」と言われたら「失礼します。」と言って部屋へ入る。
- 試験官の前で、「〇〇です。よろしくお願いいたします。」と一礼。
- その後、受験票にあるシールを剥がして渡すように指示があります。
- 椅子に座ります。「準備は良いですか?」と聞かれるので「はい。」と答えます。
- タイマーが鳴ったら覚えたお話をスタートします。
- お話が終わっても、タイマーが鳴り終わるまでは、その場で動かないようにしましょう。
もし、お話が終わらなかったら、途中で終わります。 - タイマーが鳴ったら「ありがとうございました。」とお礼を言って一礼します。
- 扉の前で「失礼いたします。」と一礼して、部屋を出ます。
お話を始めるときは、目の前に幼児の紙が貼った椅子があるので、そちらを見ながら話しましょう。(面接官の方を見ないように話します)
緊張して早口になってしまって、練習よりも時間が余る人がいるかと思いますが、笑顔で待機しましょう。

練習より10秒ほど余りましたが、合格でした!
まとめ
保育士試験の実技試験「言語」当日の流れや言語合格のポイント、合格したときの台本を公開しました!
1次試験を合格すれば、2次である実技試験は対策すれば必ず合格できます!
あともう少しなので、頑張りましょう!